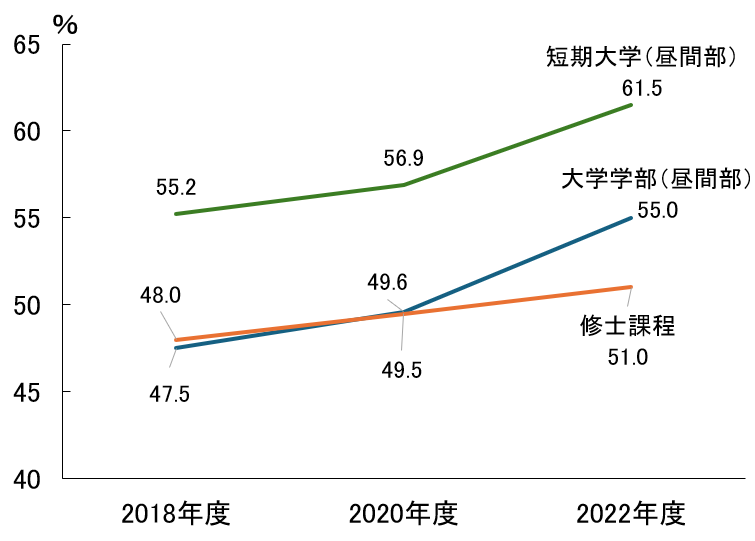マネ作品が教えてくれた本物がもたらす感動
=視覚だけでなく五感に訴える躍動感=
「これだったのか!」―。フランス駐在時、筆者はパリのオルセー美術館で"再会"した一枚の絵画を前に、思わず声を飲み込んでしまった。その作品の持つ生命力あふれる躍動感により、視覚のみならず臭覚、聴覚までもが強烈な刺激を受けたことを今でも鮮明に覚えている。
鼓笛兵の制服を着た少年、奥行きのない平坦な構図。そう、マネ作「笛を吹く少年」である。絵画にそれほど興味のなかった筆者であったが、当時小学生だった娘が油絵を習い始めていたこともあり、家族で美術館に出掛け、思わぬ"再会"を果たしたのだ。
 ロワール川と街並み
ロワール川と街並み
(写真)筆者 リコーCX5 2006年
といっても以前に「笛を吹く少年」の実物を見たわけではない。種を明かせば今から約45年前、この作品を美術の教科書で目にして以来、なぜか頭の片隅に残っていたのだ。しかしながら、本物を目の前にした時、感動と同時にある種の違和感を抱いたことも吐露せずにはいられない。
その違和感とは何か?後付けではあるが、自分なりにつらつら考えてみるとこんなことなのだろうと思う。第一に、大きさの違いである。教科書の絵はせいぜい5x3センチメートル程度だったと思うが、実物は161x97センチメートルと教科書のそれに比べて1000倍以上も大きい。第二に、本物から飛び込んでくる筆のタッチとストロークの迫力だ。教科書の絵を見てもなかなかそこまでの感動はない。第三に、絵の具の匂い、笛の音色まで伝わってくるような感覚にとらわれたことである。実物は視覚を超えて訴えかけてきたのだ。
「笛を吹く少年」との本当の出会いにより感動を覚え、その後、マネに限らず、ミレー作「晩鐘」(マルモッタン美術館蔵)、モネ作「睡蓮」(オランジュリー美術館蔵)といった印象派美術を中心にフランスでさまざまな絵画にめぐり合うことになった。さらには、それらの作品が描かれた舞台(ミレーの「晩鐘」のバルビゾン村、モネの「睡蓮」のジヴェルニー村)にも訪れた。それぞれの作品への理解が深まったと同時に、感動がより大きなものになったのである。
帰国後も、絵画に対する好奇心はさらに膨らみ、世界に2枚しか存在しないミレー作「種をまく人」の1枚が展示されている山梨県立美術館に足を延ばしたりした。
本物の絵画を鑑賞するにつれ、さらにもうひとつの違和感に気づくようになった。それは、展示環境の違いである。日本の美術館では、作品がガラスショーケースに納められていることが多い。そのため鑑賞している人の顔がガラスに映り、それが作品に被ってしまうのだ。また、ショーケースのガラスの間に枠がある場合もあり、その枠によって視野の一部が妨げられることもある。一方、筆者が知る限り、フランスの美術館では、作品はショーケースには納められていなかった。イギリス、イタリアの美術館も同様だったと記憶している。
ここで良い、悪いを述べるつもりはないが、絵画と生で対峙(たいじ)することによってもたらされる感動は、ガラス越しの鑑賞と比べると、筆者には何倍も大きく感じられる。絵画と自分の間をさえぎるものがないことで、作品から発せられる作者の思いや当時の時代背景などを直接肌で感じられるからであろう。
先述のマネ作品でも論じたように、本物に触れると五感(視覚・臭覚・聴覚・味覚・触覚)が呼びさまされる。これは何も絵画などの芸術作品に限ったことではない。フランス駐在時には、中世の城を訪れることも好きで、特にロワール渓谷の小さな街にあるシノン城は、筆者が最も感動した城のひとつである。
シノン城は、ジャンヌ・ダルクが1492年にフランス国王シャルル7世に謁見した場所である。この地に足を踏み入れることにより、その後大きく動き出したフランスの運命を少しだけではあるが自分の肌で感じることができた。
人生に感動がもっと増えたらそれだけで楽しいし、生きている甲斐が(絵画)あるはずだ。だからこそ、手間をかけてでも本物に触れる価値があるのだろう。
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!